実践可能なアイデア発想法入門9選とその評価方法

- インプットポイント
-
- 個人・チーム単位でのアイデア発想法を学べる
- 創出したアイデアの評価方法を学べる
良いアイデアが浮かばない…こんな悩みはありませんか?
ビジネスの世界において、革新的なアイデアは競争優位性を築く重要な要素です。顧客ニーズの多様化や市場環境の急速な変化に対応するためには、従来の発想にとらわれない創造的思考が不可欠です。
しかし、そうは言っても良いアイデアが浮かばず、悩む方も多いかと思います。
本記事では、個人やチームがより効果的にアイデアを生み出すための様々な発想法や、創出したアイデアの評価方法について、取り扱いやすい内容を幾つか選出してみました。この記事が、革新的なアイデアを生み出すためのヒントになれば幸いです。
目次
第1章:個人単位で効果的なアイデア発想法
その1:マインドマップ
その2:強制連想法
その3:類推思考法
その4:逆転思考法
その5:日常観察
第2章:チームで効果的なアイデア発想法
その1:ブレインストーミング
その2:シックスハット法
その3:アイデアしりとり
その4:KJ法
第3章:アイデアの評価方法
その1:事業者目線でのアイデア評価
その2:ユーザー視点でのアイデア評価
終章:まとめ
第1章:個人単位で効果的なアイデア発想法
本章では、個人単位でのアイデア発想法を具体的に幾つか紹介します。これらの手法を用いることで、固定観念から脱却し、新たな視点でビジネス課題を捉えることが可能になります。
その1:マインドマップ
マインドマップは、中心となるキーワードから連想を広げていく発想法です。中央に主要なテーマ・キーワードを書き、そこから放射状に関連する概念やアイデアを枝分かれさせていく形で、視覚的に発想を広げていきます。
この手法の特徴は、脳の自然な思考プロセスに沿った形で情報を整理できることにあります。
マインドマップを効果的に活用するためのポイントは以下の通りです。
- 主要テーマは中央に配置し、大きく目立つように書く
- 主要な枝は太く、副次的な枝は細く描く
- 色、記号、画像を積極的に使用して視覚的に表現する
- 思いついたことをすべて書き出し、後から整理する
例えば、「オンライン会議の効率化」をテーマにマインドマップを作成する場合、「技術面」「運営方法」「参加者体験」などの主要な枝を伸ばし、そこからさらに「AI議事録ツール活用」「タイムキーパーの導入」などの具体的なアイデアへと連想・発展させることができます。
マインドマップを作成することにより、思考プロセスを可視化できるため、 情報の関連性の発見にも役立ちます。
似たような発想法として、「マンダラアート」が取り上げられることがあります。中心から周囲に発想を広げていくプロセスはそのままですが、それを取り扱う枠組みが異なります。マインドマップは白紙を使用して自由に思考を広げてよい為、アイデア出しに向いているのに対して、マンダラチャートは3×3のマス目を埋めていく形で思考の整理や全体像の把握に大きく役立ちます。目的に応じて使い分けましょう。
その2:強制連想法
強制連想法は、通常であれば関連性のない概念やアイデアを意図的に組み合わせることで、新たな発想を生み出す手法です。連想から考えるマインドマップとは真逆の発想法になります
この手法の背景として、創造性は既存の要素の新しい組み合わせから生まれるという考え方があります。
強制連想法を実践するためのステップは以下の通りです。
- 取り組みたい課題や製品を明確にする
- その課題とは無関係な言葉をランダムに選ぶ(辞書やwebサイトを活用)
- 課題・製品に対して無関係な言葉を強制的に関連付ける
- 関連付けから新しいアイデアを生み出す
例えば、「オフィス環境の改善」というテーマに対して、「蝶」というランダムな単語が選ばれたとします。蝶の特性(変態する、軽やかに飛ぶ、美しい模様を持つなど)から、「オフィスレイアウトを変化させる」「軽やかに移動できる可動式ワークスペースを採用する」「視覚的に美しいオフィスデザインを採用する」といったアイデアが生まれる可能性があります。
強制連想法の利点は、思考の固定観念を打ち破り、想像もしなかった方向性のアイデアを発見できることです。特に、既存の製品やサービスに新たな付加価値を見出したい場合や、行き詰まった問題に対して斬新なアプローチを模索する際に効果的です。
その3:類推思考法
類推思考法は、ある分野の概念や解決策を別の分野に当てはめることで、新たなアイデアを生み出す発想法です。異なる分野からの知見を借りることで、固定観念にとらわれない発想が可能になります。
類推思考法を実践するためのステップは以下の通りです。
- 解決したい問題の本質を理解する
- 似たような問題が既に解決されている他の分野や状況を探す
- その解決策を自分の問題に適応できるか検討する
- 必要に応じて解決策をカスタマイズする
例えば、医療分野での手術の安全性向上を考える際に、航空業界のチェックリスト手法(パイロットが飛行前に安全確認を行うシステム)を類推して取り入れることで、手術ミスの削減に成功した事例があります。
類推思考を効果的に行うためには、幅広い知識と好奇心が役立ちます。異なる業界のケーススタディを研究したり、多様な背景を持つ人々との交流を深めたりすることで、類推のための引き出しを増やすことができます。この手法は、既存の枠組みを超えたイノベーションを求める場合や、過去に解決が困難だった問題に新たなアプローチを見出したい場合に特に有効です。
類推思考法について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください
『なぜ発明家はアナロジー思考を使うのか?具体例で学ぶ革新的アイデアの生み出し方』
その4:逆転思考法
常識や前提を意図的に逆転させて考えることで、従来の発想では生まれなかった斬新なアイデアを得ることができます。この「逆転思考」は、固定観念を打ち破るための効果的な手法です。
逆転思考のステップは以下の通りです。
- 解決したい問題や改善したい状況を明確にする
- その問題に関する常識や前提を列挙する
- それぞれの常識や前提を逆転させて思考してみる
- 逆転させた発想から実現可能なアイデアを検討する
例として、「オフィスの生産性向上」という課題に対して逆転思考を適用してみましょう。 「オフィスでは静かに集中して働くべき」という常識を逆転させると、「意図的に適度な雑音や刺激のある環境を作る」というアイデアが生まれます。 実際、カフェのような適度な雑音がある環境が創造性を高めるという研究結果もあります。
この手法を活用することにより、 問題解決に対する新しいアプローチを発見できる可能性があります。
その5:日常観察
イノベーションは必ずしも複雑なフレームワークや分析から生まれるわけではありません。日常の観察から気づきを得て、それをビジネスアイデアに発展させることも可能です。
効果的な観察のポイントは以下の通りです。
- 当たり前を疑う姿勢を持つ
- 「不満」や「困りごと」に注目する
- 気づきを記録する習慣をつける
- 定期的に異なる環境や場所に身を置く
例えば、玩具メーカーであるLEGOは、子供の遊びを観察することで、教育的価値と楽しさを兼ね備えた革新的な製品開発を行っています。子供が実際に遊ぶ様子を注意深く観察し、そこから得られたインサイトを製品改良に活かしているのです。
第2章:チームで効果的なアイデア発想法
個人の発想法だけでなく、チームでアイデアを生み出す手法も、ビジネスにおいては非常に重要です。多様な背景を持つメンバーが集まることで、単独では思いつかなかった革新的なアイデアが生まれることがあります。本章では、チームでのアイデア創出に効果的な手法について解説します。
※個人で実施可能な手法もありますが、チームで行うとより効果的なため、本章で取り扱っています。
その1:ブレインストーミング
ブレインストーミングは、最も広く知られているチームでのアイデア創出法の一つです。特定の問題や課題に対して短時間で多くのアイデアを生み出すことを目的としています。
ブレインストーミングを成功させるためのポイントは以下の通りです。
- アイデア出しの段階では、どんなアイデアも批判や評価をしない。※アイデア出しの後なら可。
- どんなに突飛なアイデアでも歓迎する。
- 質より量を重視。できるだけ多くのアイデアを出す。
- 他の人のアイデアを発展させたり、複数のアイデアを組み合わせたりすることも考える。
ブレインストーミングを実施する際には、明確な問題設定、適切な参加者数(5-10名程度が理想的)、時間制限(通常は15-30分)、誰でも発言がしやすい様な環境設定が重要です。また、出されたアイデアを全員が見えるようにホワイトボードに記録することで、アイデアの発展や結合を促進することができます。
効率的にアイデアを出したいとき、こちらの手法が役に立ちます。
その2:シックスハット法
シックスハット法は、異なる思考モードを意図的に切り替えることで、多角的な視点からアイデアを検討する手法です。6つの異なる色の帽子がそれぞれ異なる思考スタイルを表し、全員が同時に同じ色の帽子をかぶる(同じ思考モードを取る)ことで、議論の効率と質を高めます。
各帽子の意味と役割は次の通りです。
- 白色の帽子(データと事実):客観的な事実やデータに基づいて考える。
- 赤色の帽子(感情と直感):主観的に感情や直感に基づいて意見を述べる。
- 黒色の帽子(批判的思考):悲観的にリスクや問題点を指摘する。
- 黄色の帽子(肯定的思考):楽観的にメリットや可能性を探る。
- 緑色の帽子(創造的思考):創造的に新しいアイデアや代替案を発想する。
- 青色の帽子(メタ思考):冷静に議論の方向性を整理したり、次に使用すべき帽子を提案したりする。
参加者が一斉に同じ役割を演じることで、多様な角度・視点からの検討が可能になります。
その3:アイデアしりとり
アイデアしりとりは、しりとりのルールを応用してアイデア発想を促進する手法です。ゲーム形式を採用することにより堅苦しい議論の場から脱することが出来るので、創造的思考を刺激します。
アイデアしりとりのステップは以下の通りです。
- アイデアを出したい製品やサービス、課題などの基本テーマを決める。
- 参加者の一人が、テーマに関連する最初のアイデアを提案する。
- 次の参加者は、前のアイデアから連想される新しいアイデアを提案する。この際、通常のしりとりのように「言葉の最後の音」で繋げるのではなく、「概念や特徴の連想」で繋げる。
- 出されたアイデアを全て記録し、後で整理・評価する。
例えば、「オフィス向け新サービス」というテーマで以下のようなアイデアしりとりが展開するかもしれません。
Aさん「オフィスで使える植物レンタルサービス」
Bさん「植物の成長に応じてポイントが貯まるアプリ」
Cさん「ポイントを使って社内カフェでドリンクと交換できるシステム」
Dさん「ドリンクの注文をAIが最適化して配達するサービス」
このように、一見無関係に見えるアイデアも連想ゲームを通じて繋げていくことで、思いもよらない斬新な発想が生まれることがあります。また、遊び感覚で取り組めるため、チームの雰囲気も和やかになるという副次的効果もあります。
その4:KJ法
KJ法は、情報やアイデアを整理・統合するための手法です。特に多くの情報やアイデアが散在している状況で、それらを構造化して新たな発見を促す際に効果的です。
KJ法の基本的なステップは以下の通りです。
- カード作成:各アイデアや情報を1枚ずつのカードに簡潔に記入する。
- グループ化:類似性や関連性に基づいて、カードを直感的にグループ分けする。
- 表札付け:各グループの本質を表すタイトル(表札)をつける。
- 図解化:グループ間の関係性を線や矢印で表し、全体構造を視覚化する。
- 叙述化:図解をもとに、文章で全体の構造や洞察を表現する。
例えば、「新サービス開発」というテーマで各メンバーがアイデアを出した後、それらをKJ法でグループ化することで、「顧客体験向上系」「コスト削減系」「新規市場開拓系」などのカテゴリーが浮かび上がり、さらにそれらの関係性を考察することで、総合的な戦略の方向性や新たな発想が見えてくる場合があります。
各アイデア間の関係性を整理しつつ、新たな発想を促す効果が期待できます。
また、前記のブレインストーミング後にアイデアを整理する手法としても活用できます。
第3章:アイデアの評価と選定
数多くのアイデアを生み出した後に直面するのが、「どのアイデアを実際に採用するか」という選択の段階です。ここでの意思決定はビジネスの方向性を大きく左右します。本章では、生み出されたアイデアを体系的に評価し、最も価値のあるものを選び出すための方法論について解説します。
その1:事業者目線でのアイデア評価
アイデアを評価する際には、一貫した基準に基づいて判断することが重要です。評価に一貫性がなければ、主観や感情に左右された選択になりがちです。そこで役立つのが評価フレームワークです。
ここでは、取り扱いの簡単なフレームワークに絞って紹介します。
- ICE法:「Impact(影響力)」「Confidence(確信度)」「Ease(容易さ)」の3要素で評価。
- Impact(影響力): 効果や重要性はどのくらいか。
- Confidence(確信度): ポジティブな結果につながる確信度合いはどうか。
- Ease (容易さ) :低リソース(時間、金額、労力)で実現可能か。
各項目を1~10で評点し、その合計値が高いアイデアほど優先度が高いと判断します。この手法により、定量的で客観的な評価が可能になります。 - アイデアスクリーニング:2つの重要な評価軸を設定し、マトリクス上にアイデアをプロットする方法。
例えば、「実現可能性」と「新規性」によるマトリクスであれば、右上象限(両方が高い)に位置するアイデアを優先的に検討していきます。この手法により、自身の重視する評価軸でアイデアを評価可能です。
その2:ユーザー視点でのアイデア評価
最終的にアイデアの価値を決めるのは、商品を利用するユーザーです。ユーザー視点での検証なしに進めると、「作ったけれど使われない」という失敗に陥りやすくなります。
ユーザー視点でのアイデア評価法は以下の通りです。
- ユーザーインタビュー:直接ユーザーに話を聞くことで、アイデアに対する率直な反応や潜在的な問題点を発見できます。深く対話をすることで、定量的には見えてこない質的なインサイトが得られます。
- ユーザーテスト:アイデアの簡易的なプロトタイプや説明資料を用意し、ユーザーに実際に触れてもらいながら反応を観察する方法です。「思っていたのと違う」という発見が多いのも特徴です。
- A/Bテスト:特にデジタルプロダクトでは、複数のバージョンを用意して実際のユーザー行動を比較測定することで、どのアイデアがより効果的かを判断できます。データに基づく客観的な評価が可能です。
最終章:まとめ
本記事では、ビジネスにおけるアイデア発想法として、個人向けの手法やチーム向けの手法、その評価方法を幾つか取り上げてみました。
変化の激しい現代ビジネス環境において、アイデア創出能力は個人や組織の競争力を高める鍵となります。本記事で紹介した手法をぜひ実践し、自社のイノベーション力向上に役立て頂ければ幸いです。
最後に、どの発想法も「使ってみる」ことが最も重要です。一度試してみて、自分やチームに合った方法を見つけ、それを習慣化していくことで、アイデア創出の筋肉を鍛えていきましょう!
参考サイト:
https://www.kalbi.jp/ideation-tools
https://mindmeister.jp/posts/mandalachart-mindmap
参考書籍:
思考法図鑑: ひらめきを生む問題解決・アイデア発想のアプローチ60
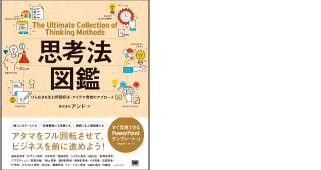
発売日:2019/10/1
著者:株式会社アンド

- マガジン編集部
- この記事はマガジン編集部が執筆・編集しました。
Contact
ファーストデジタルの提供するサービスに関心をお持ちの場合には、ぜひ一度ご相談ください。
デジタルに精通したコンサルタントがビジネスの変革を支援します。
Recruit
ファーストデジタルは成長を続けており、やりがいのあるハイレベルなプロジェクトと
切磋琢磨できるチームメンバーがあなたのキャリアアップを加速させます。


