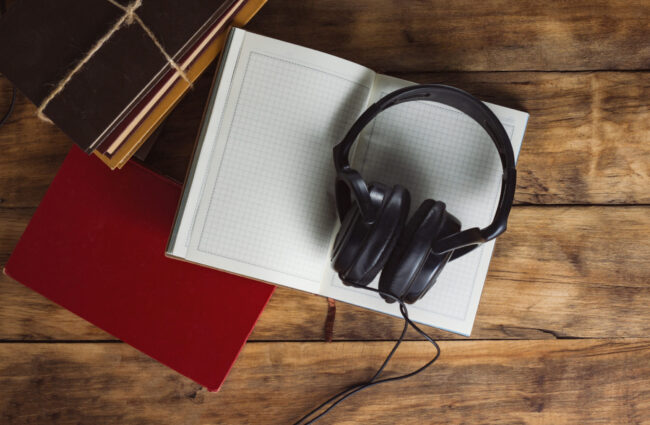【書評】なぜ、Onを履くと心にポッと火が灯るのか?

- インプットポイント
-
- ロイヤルティマーケティングの視点で、顧客との関係性の育て方を学ぶ
- コミュニティを活用したファンづくりとブランドロイヤルティの高め方を知る
- 数字に現れない“熱量”を、マーケティング戦略にどう活かすかを考える
スイス発のランニングシューズブランド「On」は、機能性に優れたプロダクトであると同時に、その背景にあるストーリーや思想に共感したユーザーによって支持され、今や世界的な人気を誇るブランドに成長した。注目すべきは、その成長が単なるマーケティング施策ではなく、ユーザーとの関係性に根ざした“共鳴のデザイン”によって成り立っている点である。
本書『なぜ、Onを履くと心にポッと火が灯るのか?』は、Onの日本展開を主導した著者が、ブランドとユーザーの間に生まれた「関係性の熱量」の正体を丁寧にひもとき、ファンが自発的にブランドを語り、育てていくプロセスの裏側を明らかにしている。ロイヤルティやコミュニティといったキーワードが、単なるトレンドではなく経営戦略の中核に据えられていることを、実体験を通じて伝える一冊だ。
FD Magazineではこれまで、ロイヤルティマーケティングの重要性とその実践方法について、以下の関連記事で継続的に取り上げてきた:
- 【書評】ぷしゅ よなよなエールがお世話になります
- 顧客と長期的な関係を築くロイヤルティマーケティングとは?
- マインドロイヤルティを可視化するNPS(ネットプロモータースコア)とは?
- ロイヤルティマーケティングを実践するには何をすればいいのか?
- 「真のロイヤル顧客」の育成方法
- アクションロイヤルティを可視化するRFM分析とは?
- 顧客を惹きつけ、ロイヤルティを高める”コンテンツマーケティング”とは?
これらの流れを受けて本書は、「ブランドと顧客の間にどう火を灯すか」という問いに対し、実践と哲学の両面から応える内容となっている。グローバルブランドの成長要因をロイヤルティの視点で学びたいマーケターやブランド担当者にとって、理論ではなく“現場から語られるリアル”が詰まった、極めて示唆に富んだ一冊である。
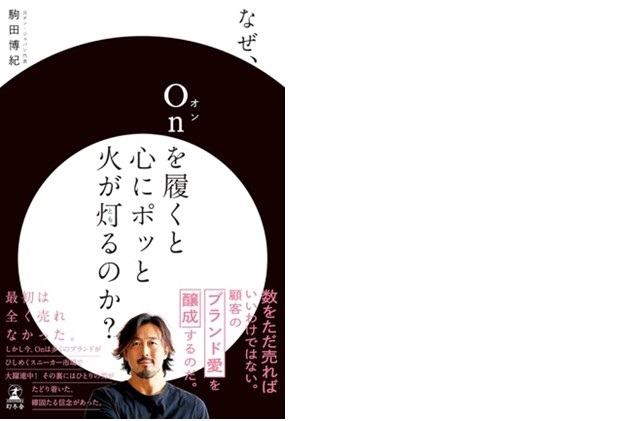
発売日:2024/3/29
著者:駒田博紀
【著者紹介・書籍の特徴】Onのブランドを日本に根付かせた実践者が語る“ファンが育つ”ブランド論
著者の駒田博紀氏は、法政大学法学部を卒業後、スイス系商社でセールスとマーケティングを経験。2013年には、スイス発のランニングシューズブランド「On」の日本展開プロジェクトに参画し、2015年にオン・ジャパン株式会社を設立。2020年から2024年にかけて代表を務め、同ブランドを日本市場に根付かせ、熱量のあるファンを生み出す独自のマーケティング戦略を実践してきた人物である。
本書では、Onというブランドが、どのようにして「履いた瞬間から心が動くような体験」を設計し、それを軸に“関係性”を育てていったのかが、駒田氏自身の実体験をベースに、丁寧かつ具体的に描かれている。
特に印象的なのは、単なるプロダクト紹介やブランド論ではなく、ブランドと人との“関係性のつくり方”に主眼が置かれている点である。商品を売ることよりも、「語りたくなる物語をどう生み出すか」「誰とどんな共体験を育むか」という視点が一貫して貫かれており、従来のマーケティング文脈とは一線を画している。
【Onの戦略に見るロイヤルティ設計】ファンが“語り手”としてブランドに関与する仕組み
Onのマーケティング戦略を語るうえで欠かせないのが、「顧客をファンとして捉え、ブランドの一部として迎え入れる」という姿勢だ。Onは従来のような「売る側」と「買う側」という一方向の関係性ではなく、ファンとの双方向のつながりの中でブランドを共に育てていくという思想を貫いている。
その象徴が、「OnFriends(オンフレンズ)」というファンの呼称である。Onのファンをどう呼ぶべきかを考える過程で、「OnCustomer」でも「OnFamily」でもしっくりこなかったという。単なる顧客以上の存在である一方で、自身の経験から「Family」という言葉に対しては慎重な姿勢をとり、最終的にたどり着いたのが「友達のような人たち」=OnFriendsという表現である。
また、Onの価値を店舗側で体現する存在として機能しているのが、「テックレップ(Tech Rep)」と呼ばれる社内チームである。これは「テクノロジー・レプレゼンタティブ(Technology Representative)」の略で、Onのテクノロジーや商品に関する理解を、店舗スタッフに伝え、店頭の体験価値を高めるための専門部隊だ。売るためのセールストークではなく、店舗と共に数字と売場体験を改善していく現場密着型のサポートチームとして、ブランド体験価値の質を支えている。
さらに、2022年には「ヘッド・オブ・コミュニティ」という役職が新設され、著者の駒田氏が任命された。この役割は、営業・マーケティング・ブランディングを横断し、ファンとの関係性をブランド戦略の中核に据えるポジションであり、グローバルでも初めてOnが設けたものである。
【感想】数字と現場のリアルを丁寧に行き来しながら、ブランドを育ててきた姿勢を学ぶ
本書を読んで感じたのは、Onが常に「数字」と「現場」を丁寧に行き来しながら、ブランドのあり方を育ててきた姿勢だ。日本市場への挑戦では、ブランド認知も売上もない状況からスタートし、試し履きイベントやスポーツショップとの丁寧な関係づくりを通じて、一歩ずつファンを増やしていった過程が語られている。ここで重視していたのは、短期の売上よりも、実際に商品を体験してもらい、ブランドを知ってもらうことだった。
また、Runtripとのランニングイベントにおいても、参加者の「イベント後の購入率」をKPIとしなかった理由が紹介されている。売上や数値では測れない参加者の体験価値を大事にする姿勢が、Onのマーケティング活動の特徴であり、これが結果的にブランドロイヤルティにつながることを意識していたことがよくわかる。
さらに、セルイン(問屋への出荷)は順調でも、セルアウト(店頭販売)が追いついていなかった問題を把握し、それを解決するためにテックレップという専任チームを正社員中心に再編成し、取扱店舗の支援を強化した経緯も描かれている。ここでも、数字の裏にある現場のリアルを丁寧に分析し、そのうえで施策を打ち直す実直な姿勢が印象的だった。
また、駒田氏自身が挑んだアイアンマン・ケアンズのエピソードも印象的だ。レースを通じて周囲からの応援や支えに助けられた体験が語られており、この経験がOnのコミュニティづくりにも通じる感覚として活きていることが伝わってくる。
まとめ
本書を通じて、Onが決して「売上の数字」だけを追い求めるのではなく、ユーザーとの接点、現場での体験、取扱店舗との信頼関係といった、小さな積み重ねを重視し続けてきたブランドだということが理解できた。
特に、Onジャパンが10周年を迎えた際の振り返りの中で語られる、「これまで現場で何を積み重ねてきたか」という視点が印象に残る。売上目標やシェア争いよりも、体験やイベント、現場の声に耳を傾け、ユーザーとの関係を育むことを優先した姿勢が、今日のブランドの強さにつながっている。
本書は、マーケティングの成果を短期的な数字で判断しがちな状況だからこそ、数字に現れない価値をどう育てるかを考えるための実践的ヒントに満ちた一冊だ。
ブランド、マーケティング、コミュニティ運営に携わる人なら誰もが学びの多い内容であり、ぜひ多くの担当者に手に取っていただきたい。
Profile


- 田中 瑞樹
- この記事は田中 瑞樹が執筆・編集しました。
Contact
ファーストデジタルの提供するサービスに関心をお持ちの場合には、ぜひ一度ご相談ください。
デジタルに精通したコンサルタントがビジネスの変革を支援します。
Recruit
ファーストデジタルは成長を続けており、やりがいのあるハイレベルなプロジェクトと
切磋琢磨できるチームメンバーがあなたのキャリアアップを加速させます。